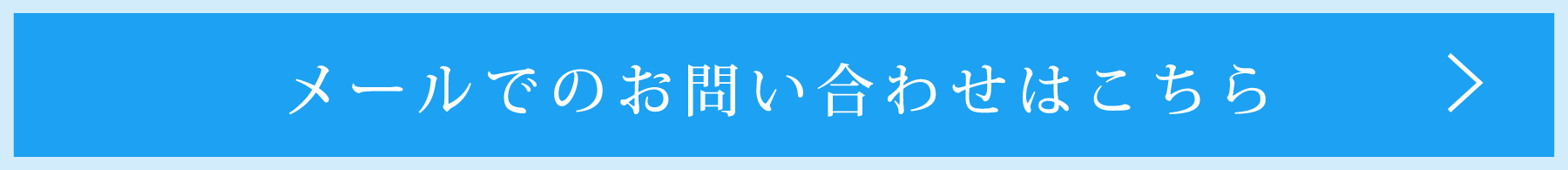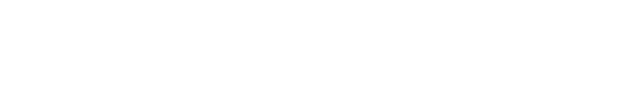- 2025.11.3
🏃♀️お子様の成長段階別:無理なく始める運動の「適期」と「ポイント」
「うちの子に運動を始めさせるベストなタイミングはいつ?」「周りの習い事と比べて、うちの子は遅れていないか不安…」
お子様の成長を願う親御さんにとって、運動開始の時期は常に気になるテーマです。しかし、ご安心ください。「早すぎ」「遅すぎ」という明確な線引きはありません。
このコラムでは、お子様の成長段階(プレゴールデンエイジ、ゴールデンエイジなど)に合わせた「適期」と、運動を「無理なく、楽しく」習慣にするための具体的なポイントを解説します。焦らず、お子さんのペースで、一生ものの運動習慣を築きましょう。
💡 運動開始に「絶対」はない!でも「適期」はある
特定の年齢で「絶対に始めなければいけない」という運動はありません。しかし、各成長段階には、その時期に適した運動や遊びがあり、それに合わせることで、お子様の能力を効果的に伸ばすことができます。
お子様の健やかな成長のため、焦らず、「発達と興味に合わせた無理のない運動」を始めることが大切です。
| 成長段階 | 適した時期(目安) | 運動の目的・ポイント | 具体的な運動・遊びの例 |
| 乳幼児期
|
0〜2歳
|
五感と全身運動の経験(後の運動の土台)を積む。 | 寝返り、ハイハイ、つかまり立ち、積み木遊び、お散歩など。 |
| 幼児期
|
3〜6歳
|
運動の土台を「遊び」の中で育む。この時期は「プレゴールデンエイジ」。 | 【3歳頃】 全身運動(立つ・座る・転がるなど)、平衡感覚を高める動き。 |
| 毎日少しでも続ける意識で、親も一緒に楽しむのがコツ。 | 【4歳頃】 縄跳び、ブランコ、三輪車など、少し複雑な動き。 | ||
| 【5歳頃】 平均台、鉄棒、簡単なダンス、鬼ごっこ、ボール遊び。 | |||
| 学童期
|
小学生
|
基礎運動能力の向上と色々な運動への挑戦。この時期は「ゴールデンエイジ」。 | 【低学年】 走る・跳ぶ・投げるの基本動作(ドッジボール、縄跳び、鉄棒、鬼ごっこ) |
| 本人の**「楽しい!」**を優先し、成功体験を積み重ねる。 | 【中学年以降】 水泳、体操、ダンス、サッカー、野球、テニス、武道など、興味のあるスポーツに挑戦。 | ||
| 思春期
|
中高生
|
自主性の尊重と生涯の運動習慣の基礎を築く。 | 部活動、ジョギング、筋トレ、ダンス、ヨガ、ピラティスなど、本人が選ぶ運動。 |
💡 親御さんが心がけたいこと
- 「まだ小さいから…」と先延ばししない: 日常生活の中で意識的に体を動かす機会を作りましょう(公園、散歩、家での簡単運動)。
- 「やってみたい」を大切に: お子様の興味や関心に基づいた運動をサポートしましょう。
- 親自身が楽しむ姿を見せる: 親が運動を楽しむ姿は、お子様にとって最大のモチベーションになります。
運動を始めるのに「絶対の年齢」はありません。お子様のペースを見守りながら、無理なく「体を動かす楽しさ」を伝えることが最も大切です。